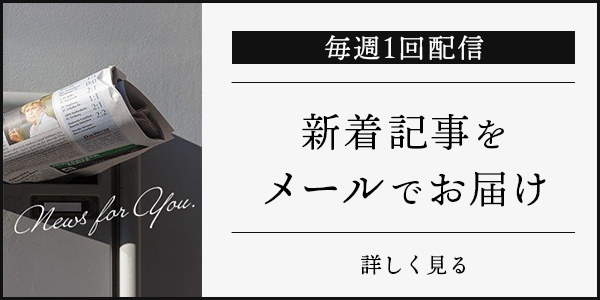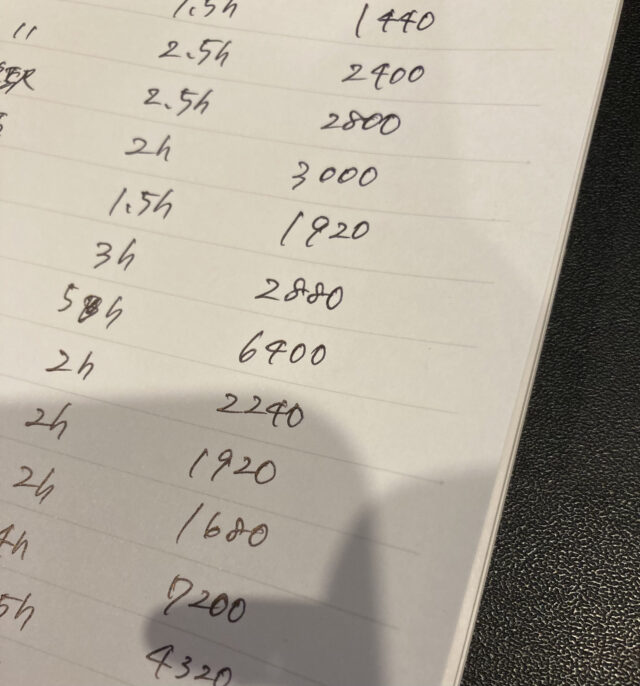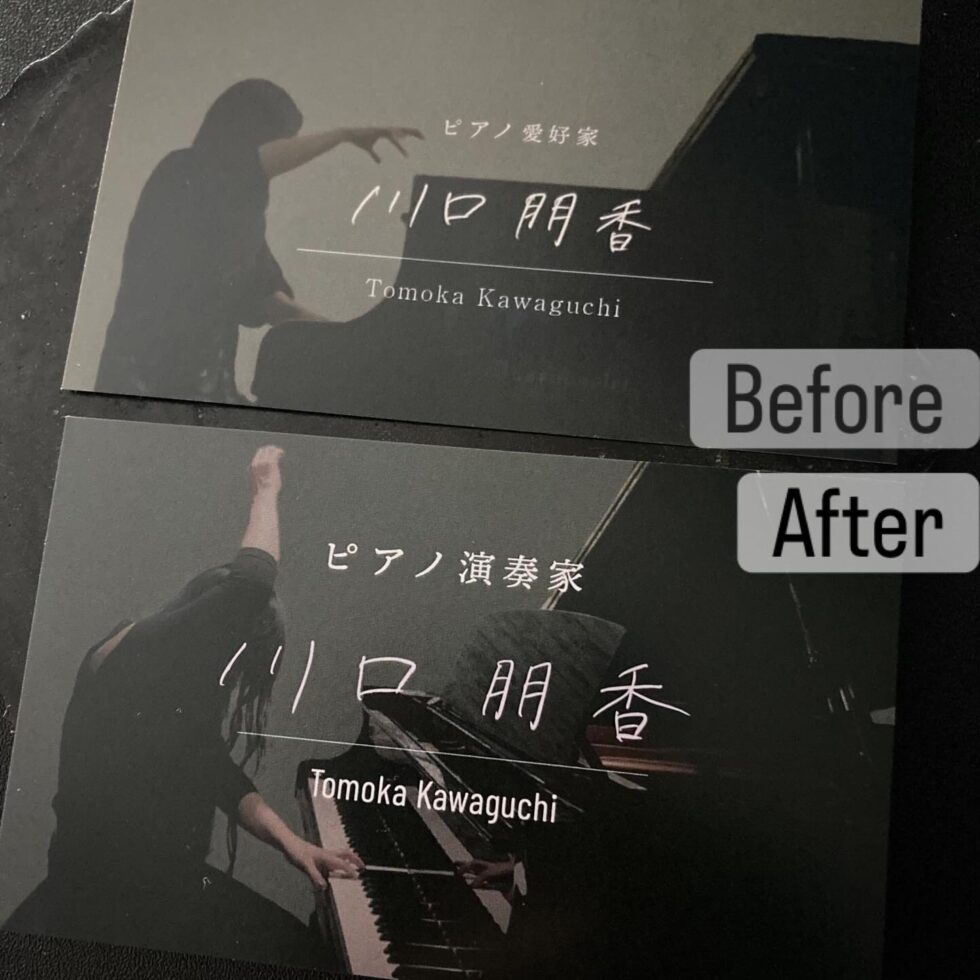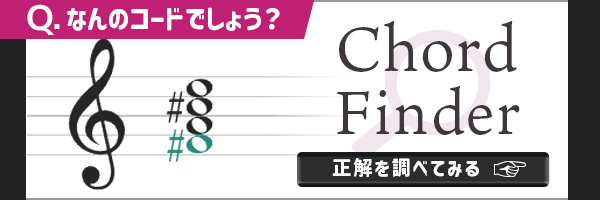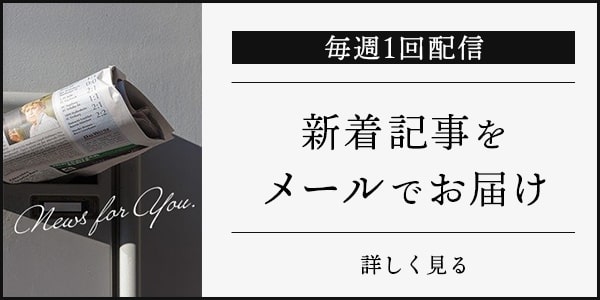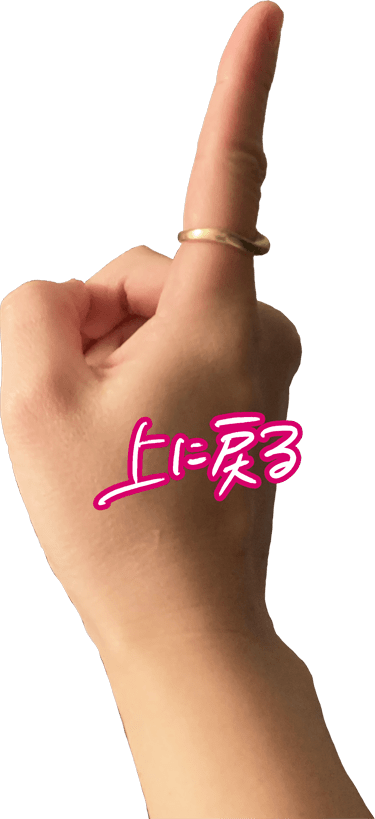こんにちは、ピアノ弾きカワグチです!
最近、背伸びしてとある分厚い経済の本を読んでいまして。
いや、正確に言うと、読み切れなくてメルカリに売ったのですがw
その本を、売る前に最後にちらっと開いてみると
「クラシック音楽」という言葉が目に入ってきました。
経済書でクラシック音楽?と思って読んでみると
ベートーヴェンの時代と比べて
クラシックの交響曲を演奏するために必要な楽団の人数はほとんど変わっていない
つまり、クラシック音楽は昔から生産性が改善されていない、とのこと。
(ボーモル病とか、ボーモルのコスト病というらしいので
気になる方は調べてみてくださいね)
…たしかに。
音楽って非効率?
楽譜が手書きから製本されたり
最近ではタブレットなどで電子的に見ることができたり
飛行機や電車の普及で、コンサートやレッスンへの行き来がしやすくなったり
周辺環境は便利になったものの
暗譜するのに要する時間とか、本番の演奏する時間とかって
昔と変わっていないでしょうし、あまり縮めようがないですよね。
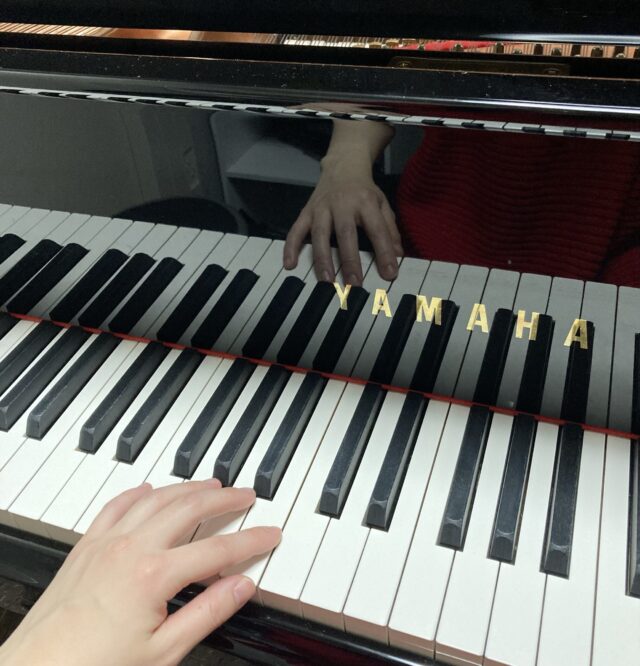
むしろ、楽譜も手書きだったであろう時代に
あれだけ大量の曲を生み出したショパンさまって凄すぎると思うんですよね。
しかも、書けるということは、その曲を弾けるわけでしょうし。
人対人のサービスは時短・効率化しにくい
ボーモル病の起源はクラシック音楽らしいですが
経済や社会学の分野では、教育や医療など
いわゆる人対人のサービスでよく論じられるそうでして。
わたしは前職で医療現場で働いていまして
特に、機械を扱うことも多いお仕事だったのですが
その時もす~ごい思っていたんですよね。
仕事は機械化されて、近い将来、人いらなくなるんじゃないか。
1日に何十回も同じ説明をしていたので
人が通ったら、自動でしゃべってくれる機械開発されないかなぁと。笑
(ありそうですよね)
一方で、仕事以外のボランティア的な仕事にめちゃくちゃ時間を取られ
(理不尽なクレーマーの対応や、話しまくるおばあちゃんの話を傾聴したりなど)
しかも、そこはいくら一生懸命対応しても、価値も評価もつかない。
医療費は一律ですし、医療従事者は美容師さんのように指名制ではないですしねw
ということは、自分は社会的に価値にならないことに心身を費やしているんじゃないか…
という虚しさを常に感じていました。
生産性が低いものは
「悪」なのか
と言う感じで少し脱線しましたが
効率の悪いものはじゃあ、なくなればいいのか?

この効率化社会で、音楽ってお荷物なんでしょうか…
だったら申し訳ない…
というと、そうじゃないですよね。
医療や教育に関しては、テクノロジーや政策で改善の余地がありそうな気がしますが
音楽に関しては、そうじゃないから音楽家や音楽愛好家が今も絶えずいるのでしょう。
時間を短縮する技術と
時間をかける贅沢
むしろ、その時間の長さに
価値を感じるものってあるはずで。
ダラダラ長ければ長いほどいい、というものでもありませんが
コンサートやライブが30分で終わったら、物足りないでしょうし
倍速再生すればいいもんでもない。
同じ食事にしても、
忙しいスキマ時間に10分でサクッと食べられる
ファストフードや立ち食いそばが便利な一方で、
ラグジュアリーなディナーで、料理がせかせかと運ばれてきて
「60分で退席してくださいね」とか言われたらちょっと味気ないでしょうしw
「時間をかけないのがいいこと」のものがある一方で
「急がない贅沢」というのもあるんじゃないかなぁと。

芸術家にマイペースな人が多い理由
音楽に限らず、周りを思い出してみると
絵が上手な人とか、独特の才能がある芸術家肌の知人って
時間にルーズな人が多い気がするのです。
しかも、毎回待ち合わせに30分遅れてくるとか
学校や会社に遅刻して午後から来るとか
そのルーズさもハンパないんですよw
時間効率なんて考えたら生み出せない
というのも、これは悪口ではなくて
(というか、実はカワグチも学生時代は遅刻魔だったのを
必死に矯正して今に至るので、あまり人のことは言えない)
何かを作るとか生み出すっていうのは、それだけ
時間効率度外視で初めて成り立つんじゃないかな、と思うんです。
少ない時間で多くの作品・いいものを生み出せるに越したことはないかもしれませんが
創作活動って、工業製品を量産するのとは違って
綿密に計画を立ててその通りに動けば、というものではないでしょうし、
「考える」「感じる」時間を飛ばしてしまうと
それはただの、どこにでもある大量生産品ですもんね。

そういう人を、生産性だとか、時間にきっちりだとか
そういう型にはめて、軽々しく社会人失格だとか責めてしまうのは違うよなぁと。
ただ、待ち合わせには来てほしいので
その人にだけわざと30分早い時間を伝えておいたりしますけどねw
結論:時短・効率化が
全ての分野でベストとは限らない
結論、
全ての分野で「時間を短くすること=良いこと」
という考え方を適用しちゃうのがナンセンスだよな、と思ったりします。
効率重視で時短できる分野がある一方で、
縮められない、縮めないことにこそ価値がある分野もある。
それを、うまく共存させられたらいいですよね。
縮めることに価値があるもの
一方で、エクセル計算のように
何度も同じことを繰り返す単純作業だったり
人間の体力や精神力をネガティブな意味で消耗してしまうものに関しては
エクセルのシートをみてうっとり、という人は少ないでしょうから
極力短縮して効率化したほうがいいでしょう。
楽しみはなるべく長く、いやなことは減らす。
ということで、効率化や生産性を追求するからには
働く時間を減らして音楽を楽しむ時間が増える、
そんな社会になったらうれしいなと思うのでした(^^)/
読んでいた経済書はこちら
ちなみに冒頭の
カワグチが読み切れなかった本はこちらです↓


本記事のボーモル病については少し紹介されていたにすぎませんが
金融分野に興味のある方はよかったらどうぞ!
読み切ってないからレビューはできませぬ(^O^)
この記事をシェアする
記事のシェア・ご紹介はご自由にどうぞ◎


 (3 いいね)
(3 いいね)